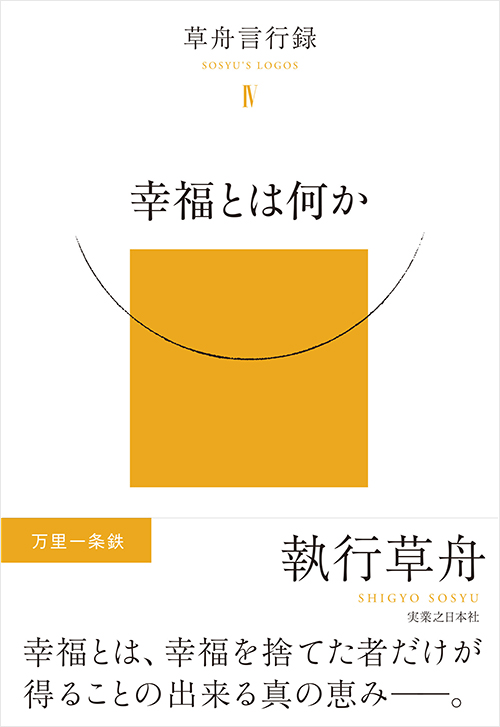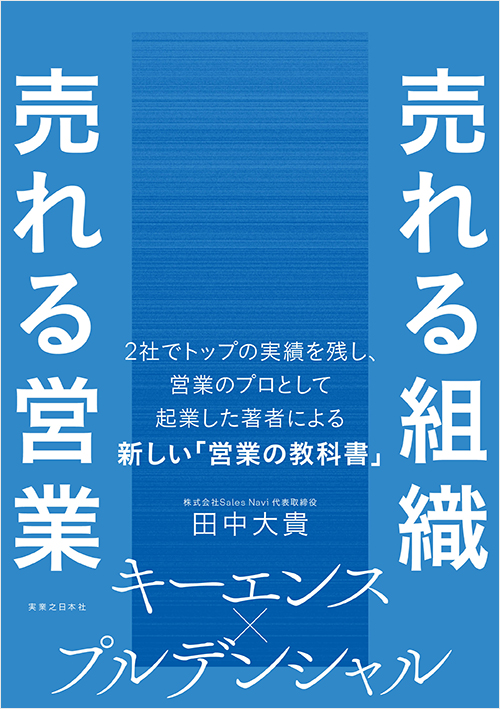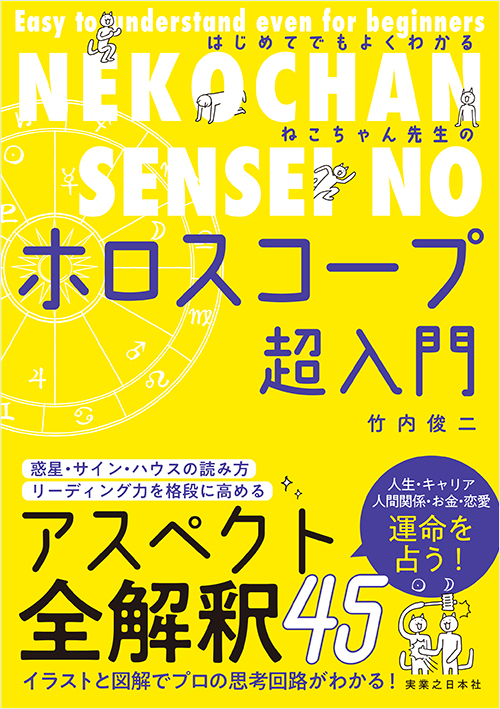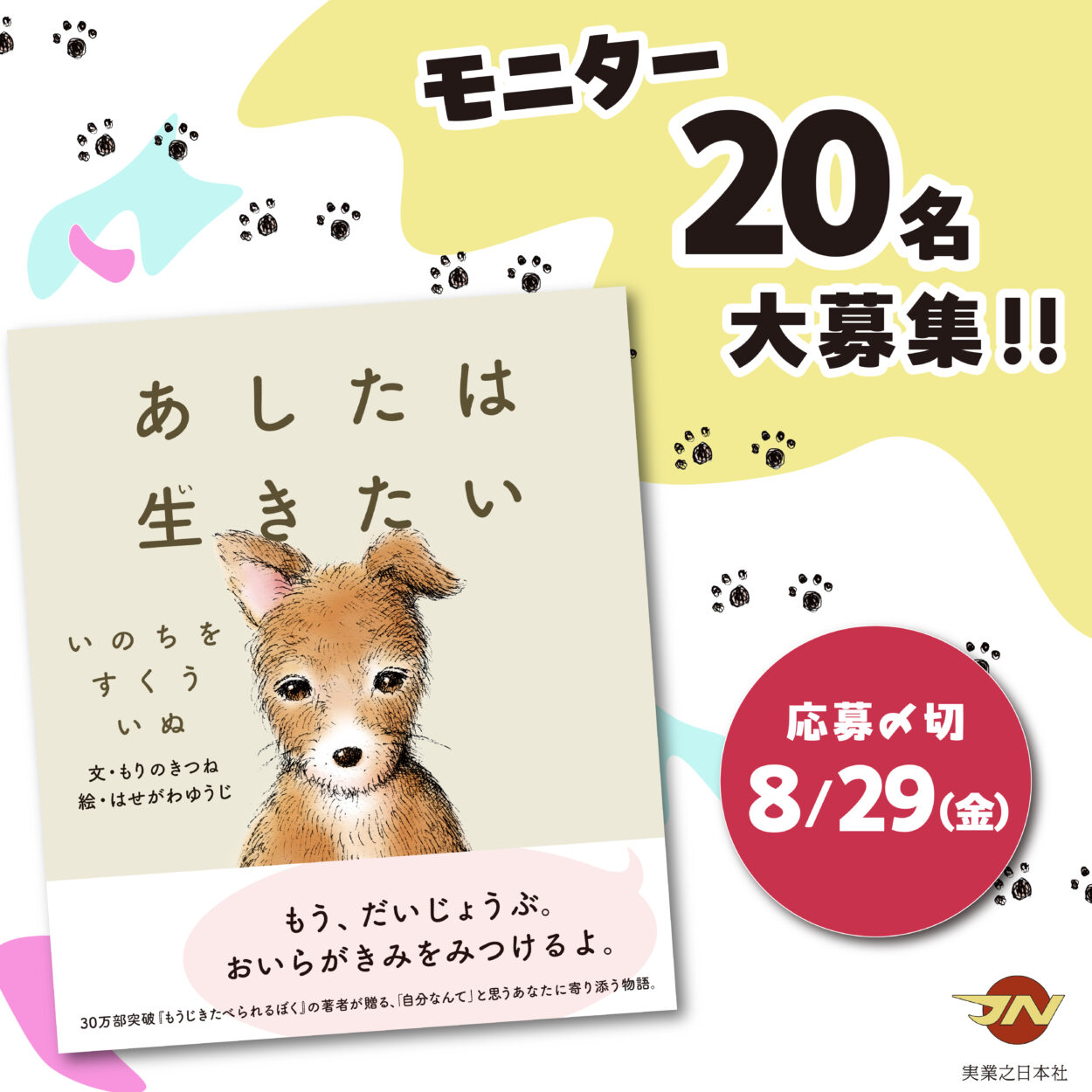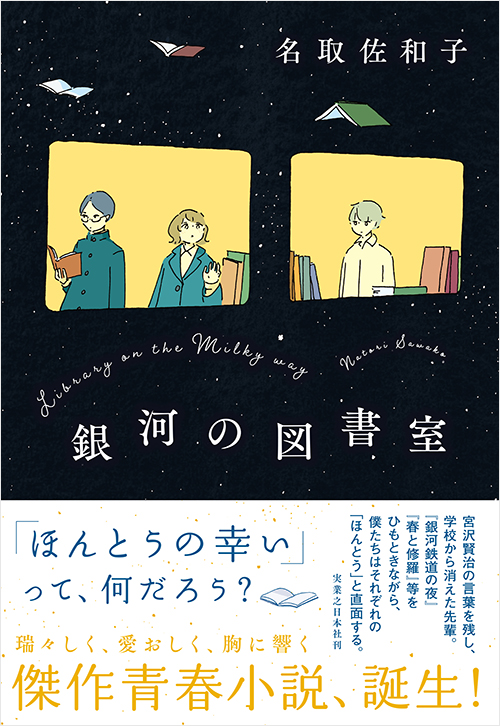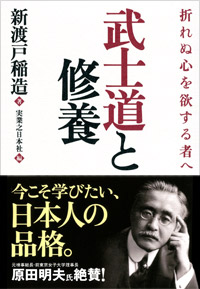
武士道と修養 折れぬ心を欲する者へ
新渡戸稲造著(ニトベ イナゾウ)
実業之日本社編(ジツギョウノニホンシャ )
四六判上製 208ページ
2012年08月30日発売
価格 1,650円(税込)
ISBN 978-4-408-10944-2
在庫なし
100年を経て、今なお光り輝く、新渡戸哲学の決定版。
日本人の原点がここにある――
新渡戸稲造博士、生誕150周年 記念発刊! 本書は、本年2012年9月に生誕150年を迎える新渡戸稲造博士の大ベストセラー『武士道』『修養』から、「克己」をテーマとして項目を精選、現代仮名遣いを用いた平易な日本語にして再編集、新たに編んだものです。明治・大正・昭和の時代、国の復興・発展に尽力した“真の国際人”新渡戸博士の教えは、多くの人々に大きな感化を与え、今もまったく色あせることはありません。ページを繰るたびに名言に巡り合える、深い示唆を与えてくれる1冊です。 元検事総長・前東京女子大学理事長 原田明夫氏による「発刊に寄せて」を収録。 ●「もっとも進歩的思想を持った日本人でも、その皮膚を一つ剥けば、 たちまち一人の武士の姿をあらわすであろう」 ●「戦場でよい敵となるにふさわしい者は、平時において親友とする値のある者である」 ●「日本の武士道というものは、それを象徴する桜と同じく、我が国に固有の花である」 ●「困難はいつか快楽に到達する順序であると思うのだ。 そうすれば困難に遭遇しても落胆することなく、かえって愉快になり勇気が湧く」 ●「勇気の修養には進むほうの勇ばかりでなく、退いて守るほうの勇も養うように心がけなければならない。 両者がそろって本当の勇気ができるのである」……(すべて本文より) 目次 【修養篇】 ■第一章 折れぬ心を欲する者へ(『修養』第五章「勇気の修養」より) 臆病な僕でも勇気を持つことができた 不遇の祖父、罰を受けた父が教えてくれたもの ほか ■第二章 敵を見極め、己に克つ(『修養』第六章「克己の工夫」より) 「克つ」と「勝つ」は異なる概念 人の持つ「色気」が一番の問題 ほか ■第三章 天を楽しみ地を楽しんで、世を渡る(『修養』第十三章「道」より) 緩やかな傾斜を大勢で登ることも貴い 「給料に見合う仕事しかしない」ことの愚 ほか 【武士道篇】 ■序文 僕が『武士道』執筆に至った動機(『武士道』「原序」より) ■第一章 武士道とは何であるのか(『武士道』第一章「武士道の倫理系」より) 桜と同じ我が国固有の花 武士たちの心に刻まれた確たる行動規範 ほか ■第二章 武士道の源にあるもの(『武士道』第二章「武士道の淵源」より) 仏教の影響―生に執着しない気概 神道の影響―忠誠心と愛国心 ほか ■第三章 正義―もっとも厳しく、率直で男らしい徳(『武士道』第三章「正義」より) 武士道の中で一番厳しい掟 義理とは鞭を持った厳格な教師 ほか ■第四章 勇気―勇敢で冷静沈着な心(『武士道』第四章「勇気」より) 真の勇気とは「死ぬべきときにのみ死ぬこと」 勇気を極めれば仁になる ほか ■第五章 仁―君主たる者が持つべき資質(『武士道』第五章「仁」より) 王たる者が備える徳 武士が詩歌や音楽をたしなむ理由 ほか ■第六章 礼―人に対する同情の優美な表れ(『武士道』第六章「礼儀」より) 相手の感情を思いやる心の表れ 贈る品物を尊ぶアメリカ人、贈る気持ちを尊ぶ日本人 ほか ■第七章 誠―地位の高い者の徳(『武士道』第七章「至誠」より) 何よりも重かった「武士の一言」 遠く離れたところにある武士道と商業道 ほか ■第八章 名誉―恥を知り、試練に耐える(『武士道』第八章「名誉」より) 「恥を知れ」が最大の戒めである理由 寛容と忍耐が武士の行き過ぎを抑制した ほか ■第九章 忠節―命をかけて守るべきもの(『武士道』第九章「忠節」より) すべての行為の根底に「忠」がある 忠心とへつらいはまったくの別物 ほか ■第十章 現在に活かす武士道―不死鳥のように蘇る(『武士道』第十七章「武士道の将来」より) すべての日本人が武士の魂を内包している 武士道の教えは永遠に続く ほか